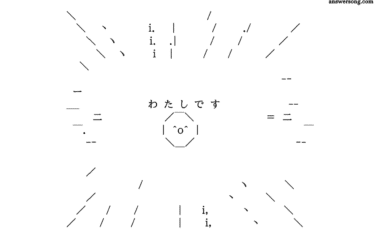お風呂場で子どもの泣き声を聞くと安心する。泣き声が聞こえるなら呼吸ができているってことだし溺れてはいない。ただ泣いているならただでさえ前が見えていないりおぴょの視界が涙でぼやけているというか私と同じで目を開けていない可能性が高い。私が頭上からシャワーを浴びて髪を両手で撫でながらシャンプーを洗い流している最中に、つまり私が目を離している隙になにもない場所でさえ転ぶりおぴょが滲んだ視界のなかシャンプーの泡で足を滑らせて床に頭をぶつけて泣き声がやんでしまう可能性がある。お願いだから私が髪を洗っている間は一生泣いていてほしい……とりおぴょが泣いている理由を無視して感慨に耽っていたら罰が当たったのか、
「いッッた」
りおぴょに思いっきり髪を引っ張られてめちゃくちゃ痛かった。子育てを始める前だったら泣いていた。でも子育てを始めたあとは怒りしか湧かない。怒りは人を強くする。どうして世の中のパパやママがあんなに怒りっぽいのかいまならわかる。子どものやることなすことにいちいち泣いて挫折して子育てを投げ出さないために怒っている。私はシャワーでシャンプーを洗い流して怒りは水に流せずにイライラしながら水を止めて目を開いて状況を把握した。
愛する我が子、りおぴょは怯えきった表情で私の背後を指差して泣きじゃくっていた。
私が振り向くと壁際でなんか黒いカビみたいなものが蠢いていた。
よく見るとデカい蜘蛛が張りついていた。
私の家で見かけた蜘蛛のなかでは歴代最高レベルのデカさだった。しかも浴室で蜘蛛を見たのは初めてじゃないか? さて、どう見てもあのぴょんぴょん跳ねて私が唯一可愛いと認める虫、ハエトリグモではないが……その10倍ぐらいはデカいが……アシダカグモみたいな鎧感もない。なんだこの蜘蛛? 黒くてデカくて丸くて、なんか自分の足食ってない? タコも自分の足を食べるというが、まさにこの蜘蛛の丸みを帯びたフォルムはタコだった。
「黒い……タコさんだね」
私は私の背後に隠れるりおぴょに話しかけた。子どもはタコが好きだ。どれぐらい好きかというと、わざわざウインナーをタコさんウインナーにして食べたがるぐらい。
「ちがう……」
りおぴょは泣きながら首を振った。震えた声と迫真の顔が面白すぎて私は笑った。
「違うの? どこが?」
よく見て、と私は蜘蛛を見て、りおぴょの視線を誘導した。蜘蛛は相変わらず脚をもぞもぞ丸めて口元へと運んでいる。時折脚を交代させているのを見ると自分の足を食べているわけではないし怪我をしている様子でもない。猫みたいに舐めて清潔にしているのか、足についた水滴を啜って水分補給をしているのか?
そうして蜘蛛を観察していると、いつの間にか私の苛立ちは消えていてりおぴょの泣き声も鼻息が荒い程度に収まっていた。動物には癒やしの効果があるというが、蜘蛛にもあるのだろうか? まあタコにあるなら蜘蛛にあってもおかしくはない。
「ほら、タコさんの脚は8本でしょ? このタコの脚も8本あるし、タコさんでしょ?」
「ちがう……」
りおぴょは私のこの蜘蛛タコ説を頑なに受け入れようとしない。一番バカでアホで物を知らない親に逆らう力もない愚かで無能な子どもの時期のくせに、簡単に騙されないとはかわいげがない。が、それはそれで将来有望だと思えばかわいい(親バカ)。
「なんで?」
「かたかった」
「え、触ったの!?」
私がビックリして訊き返すと、りおぴょの鼻息が泣き声に変わり始めて嫌な思い出をフラッシュバックさせてしまったのだと察した。あ~もう泣かないで、なに、どうしたの? りおぴょの涙をお湯で洗い流しながら事情を訊く。気がついたら腕にいたの? 蜘蛛が?
私はりおぴょが自分の腕を這う蜘蛛を発見してびびり散らかして発狂しながら腕をぶんぶん振り回して蜘蛛を振り落としたあと泣いている場面を想像して笑いをこらえることができなかった。どうして子どものハプニングってこんなに面白いの?
「じゃあこれがタコじゃないなら、なんだと思う?」
「むし」
「そうだね。これはクモっていう虫なんだけど……虫は嫌い?」
「うん」
「タコは好き?」
「うん」
「クモは?」
「嫌い」
「なんで?」
「キモい」
「タコはキモくないの?」
「うん」
「なんで?」
私はタコを想像した。どう考えてもキモい。目の前の蜘蛛と比較すると、たしかにこの蜘蛛はタコに似ているがタコみたいにうねうねしていない。目もギョロっとしていない。吸盤で張りついてきたりしないし墨を吐いてきたりもしない。脚もタコよりはしゃきっと伸ばしている。実際壁に張りついているのが蜘蛛ではなくタコだったら、私ものんきに観察なんかしている場合ではなかった。びびり散らかしてお風呂場の外に緊急脱出していただろう。さすがに全裸でタコと対峙する勇気は大人になっても身につかない。大人でも江戸時代の春画みたいになったら泣く。
「タコはキモくない」
と説明能力を持たないりおぴょはいう。わかってるよ。この子はタコさんウインナーも好きだし、たこ焼きも好きだし、お寿司のタコも好き。つまり「タコ」といえば生きているリアルなタコより、可愛くて動かなくて食べられるタコを想像している。一方で目の前の蜘蛛は生きていて食べられそうにない。どころか逆に食べられそうぐらいの恐怖を抱いているのかもしれないが、
「タコのほうがキモいよ」
私はお風呂場の扉を開けた。蜘蛛が物音にビビって俊敏に移動する。りおぴょもビビって短く悲鳴を上げた。私は洗面所からiPhoneを持ってきてタコのリアル画像を検索してりおぴょに見せた。
「よく見て、これがタコだよ。タコのほうがキモくない?」
「……キモくない」
「本当に?」
「うん」
「そう? ほら、冷めるから湯船に入って。クモは大丈夫だから」
私はりおぴょを湯船に入れて訊く。
「じゃあカニさんは好き?」
「うん」
「エビは?」
「好き」
「よく見て、これがカニだよ」
私はiPhoneでカニのリアル画像を検索してりおぴょに見せた。それからエビのリアル画像も見せた。
「カニもエビもキモくない?」
「うん」
「でもクモはキモい?」
「うん」
「ふうん。じゃあもし、このタコとカニとエビが……」
と、私は改めてタコとカニとエビのリアル画像をりおぴょに見せてから天井を指差した。
「上から落ちてきたらどうする?」
「落ちてこないもん」
りおぴょは不安そうに天井を見上げたあとしばらく固まったが、唾までは固まらなかったらしく喉を滑り落ちて飲み込んだときのごくりが丸見えだった。天井では換気や浴室暖房を行う暗闇が口を開けていて、りおぴょはその暗闇の奥を見ている。
「じゃあ今度、タコとカニとエビを買ってきて、お風呂に入ってるときに上から落ちるように置いといてもいい?」
「ダメ~」
といいながら、りおぴょは首をふりふり振ってトルネードが着地するみたいな動きで視線を下ろして私と顔を合わせる。こういう子どもの素直で無邪気でかわいい反応を見るたびに思うのだが、私にも上を指差されれば上を見て、否定するときには一生懸命首を左右に振っていた時期があったのだろうか? だとすれば、私はいつからかわいくなくなったんだろうか? りおぴょもいつかはかわいくなくなるのだろうか? かなしい。
「なんで?」と私は訊く。
「なんでそんなことするの?」りおぴょが逆に訊いてくる。
りおぴょは私の目をまじまじと見つめてきて責める……ように私が感じているだけかもしれないが、ちょっと、そんな純粋な目で見ないで。私や私が適応した世界は死んだタコみたいに淀んだ目でアイコンタクトをするんだよ。そんな綺麗な目で見つめられたら、塩をぶっかけられたナメクジみたいに蒸発してしまう。水清ければ魚棲まずという言葉を知らないのか?
「なんでって……」頑張れ私。大人をナメるな。「好きなんでしょ? タコが」
「好き……」
「嫌いなものを買ってきて置いたら意地悪だけど、好きなものを買ってきて置いてあげるんだから、嬉しいんじゃない?」
「えぇ~、うぅ~ん……」
りおぴょは困ったように唸り、iPhoneに表示されたリアルタコ画像をちらっと見た。私はiPhoneを手に取って操作した。
「よく見て、これがタコだよ。これが触ってきたらどう思う?」私はYouTubeで検索したリアルタコ動画を見せた。
「うぅ~~~~……」
りおぴょのなかのかわいいタコさんと、生きて動いているリアルなタコがせめぎ合っているのがわかる。それからりおぴょは、観念したように呟いた。
「ちょっとキモい……かも」
「キモい? タコさんが?」
「うん……」
りおぴょは渋々といった様子で、しかしはっきり認めた。やった! 私の勝ちだ! 嗚呼、こうして私は愛する我が子を汚していかなくてはならない。汚れた水のなかでは、綺麗すぎるほうがキモいのだから。
「でも最初はキモくなかったのに、どうしてキモくなったの?」
「う~ん、動いてるから……」
「動いてるから?」
「わからない」
りおぴょは自信なさげに笑みを浮かべた。そうだね。もうこの子は、こんな感じで私が訊き返すとき、下手にうなずくと汚い反論が飛んでくると学習しているかもしれない。「動いてるから?」「うん」「じゃあ私も動いているけど、私もキモいの?」。かわいそうに、りおぴょはまだ反抗期を迎えていないから親に向かって「キモい」とはいえない。
「本当はね」
私はりおぴょから「わからない」を引き出すとなるべく答えを教えるようにしている。自分の頭で考えさせるようなバカな教育方針は採っていない。だって子どもはバカなんだから、バカに考えさせたらバカの考えが身につく。つまりバカに育つ。どうせ子どもなんて四六時中バカなことばっか考えているんだから、私がそばにいるときぐらいはもう少しマシな考えを授けるのが親の務めだ。
「タコさんはキモくないよ」
「えっ?」虫を見つけたときに鳴く猫みたいな声で驚くりおぴょはかわいい。
「タコさんは勝手におうちに入ってこないでしょ?」
「うん」
「でもクモは?」
そこでやっと蜘蛛の存在を思い出したりおぴょが壁を見る。まだ蜘蛛は張りついている。
「入ってくる……」
「そう。クモは勝手に入ってくるし、勝手に触ってくる」
そしてほかの勝手に入り込んだ悪い虫を抹殺してくれるから私は好きなのだが、りおぴょに益虫の概念を理解させるのはまだ早い。実際、勝手に入ってきて勝手に触られて泣かされたりおぴょの立場からすれば、蜘蛛は害虫でしかない。
「つまり、人の場所に勝手に入ったり、人の身体に勝手に触ったりするやつはキモいってこと。それがクモじゃなくても」
私は極めで当たり前のことを教えているつもりだ。それこそ子どもに教えるようなことを子どもに教えているだけだ。でもこの汚れた世界では、こんな当たり前のキモさも学ばずに育った害虫が多すぎる。きっと子どもの頃に「キモい」なんて汚い言葉からは隔離されて大切に育てられたんだろう。気持ち悪い。
「りおぴょはそういうことしないよね?」
「うん」
素直に頷くりおぴょの顔はお風呂で温まって茹でダコみたいになっている。それでいい。私は子どもを蜘蛛には育てない。タコに育てばいい。